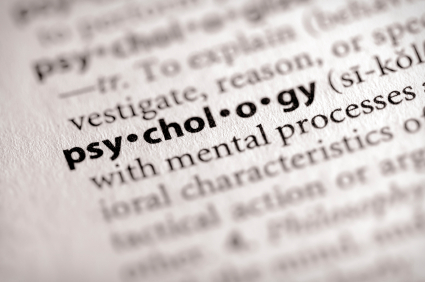
�l�X�ȐS���Ö@
�Ȃ����l�ȐS���Ö@������̂�
�S���Ö@�̎��
�@�\�w�S���Ö@�n���h�u�b�N(�����ق�(��), 2005)�x�̖ڎ��ł̕���
�@�@1. ���W���[�Y�h
�@�@2. ���_����
�@�@3. �����O�h
�@�@4. �s���Ö@
�@�@5. �Ƒ��Ö@�w�h
�@�@6. �V�Y�Ö@
�@�@7. ����Ö@
�@�@8. �C���[�W�Ö@
�@�@9. �F�m�Ö@
�@�@10. �F�m�s���Ö@
�@�@11. �Ö��Ö@�E�����P���@
�@�@12. �A�h���[�S���w
�@�@13. �Q�V���^���g�Ö@
�@�@14. �g�����X�p�[�\�i���Ö@
�@�@15. ���ϗÖ@
�@�@16. �X�c�Ö@
�@�@17. �u���[�t�Z���s�[
�@�@18. �x���I���_�Ö@
�@�@19. �𗬕���
�@�@20. �Տ�����@
�@�@21. ������
�@�@22. �|�p�Ö@�E�\���Ö@
�@�@23. �t�H�[�J�V���O
�@�@24. �G���J�E���^�[�E�O���[�v
�@�@25. �T�C�R�h���}(�S����)
�@�@26. �T�C�R�G�f���P�[�V����(�S������)
�@�@27. �i���e�B�u�E�Z���s�[(����Ö@)
�@�@28. �O���[�v�Ö@
�S���Ö@�̑��l���̗��R
�@�\�l�Ԃ̑��l���A�����A�Љ�A�l�̐l�ԓI�����̑��l�������邽��(��, 2011)
�@�@�\�S���Ö@�Ƃ͐l�ԓI�R�~���j�P�[�V�����ɂ��W�̔�����
�@�@�@�\�K�R�I�ɁA�l�Ԃ̕����̔��ׂȗl���Ɋւ��
�@�\�S���Ö@�́A���ɐ藣���ꂽ���̂ł͂Ȃ��A���̂Ȃ���̗l�q�����G�ł��邽��(��, 2011)
���_���͗Ö@�Ƃ́H
���_���͗Ö@
�@�\�n�n�҃t���C�g(Freud, S.)�Ƃ��̌�p�҂̐��_�Ö@
�@�@�\���`�̐��_���͗Ö@�̓t���C�g���_�݂̂��w�����A�L�`�ɂ͂��̌�̔��W�Z�@���܂�(�g���_���͓I�S���Ö@�h�Ƌ�ʂ��邱�Ƃ�)
�@�@�\�t���C�g���_�̔��W�̗��j�̒����瑽���̐S���Ö@���_���a�����Ă���
�@�@�@e.g., �A�h���[���_�A�����O���_�A�T���o���E�t�����̐V�t���C�g�h�̏����_�A����S���w�A�N���C���̗��_�A
�@�@�@�@�@�@�ΏۊW�_�A���ȐS���w�A���J�����_etc�c�c
�@�\�S�̎����̏Ǐ�ɂ́A�}�����ꂽ���ӎ��I�Ӗ�������Ǝ咣����
�@�@�\���_���͗Ö@�͖��ӎ��ɂ�����̂ɋC�Â��A������u���@(�ӎ���)�v���鎖�ōs����
�@�\���_���̖͂ڕW�́A���ӎ��ł���l�X�Ȋ�]�E�~���̈ӎ��������邱��
�@�\���_���͂̔��W�ɔ����A���R�A�z�@�A��R�A�]���A�]�ځA�r�̍�ƁA�G�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X���̊�b�T�O�����炩�ɂ��ꂽ
�@���_���͂�3�̈�
�@�@�S���w�I�𖾖@; ��{�I�ɂ͎��R�A�z�@�ɂ�閳�ӎ��I���@�̉�
�@�A���Õ��@; �핪�͎҂̖��A�ӎ����ւ̒�R�A�]�ځA�S�I�����ւ̎��Î҂̉��߂ɂ�铴�@�u���I���_�Ö@(���_���͗Ö@)
�@�B�@�A�A���瓾��ꂽ�S���\���I���B���_�ȂLj�A�̐��_�a���w�I���_(���_���͗��_)
�@�t���C�g���_�Ƃ��̌�̗��_�̈Ⴂ
�@�\�t���C�g�ɂ�錴�@�́A�ÓT���_���͂ƌĂ�A���݂̑Ζʖ@�ɂ�鐸�_���͗��_�Ɋ�b��u�������_�Ö@�Ƌ�ʂ����
�@�@�\�핪�͎҂͐Q�֎q�ɉ��ɂȂ�T4�`5���ʂ��Ď��R�A�z�����邱�ƂƋ֗~�K������邱�Ƃ����߂�ꂽ
�@�@�\�Ώۂ͐_�o�ǂ𒆐S�Ƃ���l�Ɍ����A���ԓI�E�o�ϓI���S�ƂƂ��Ɏ��Â������Ԃ�v����
�@�@�\�Ώۂ͐_�o�ǂ̐��l���҂݂̂ł�����
�@�@�@�\�ÓT�I�ɂ́A���҂ɂ͎��Âւ̓��@�Â��������A�a��������A������x�̒m���̍����Ǝ���̋��������邱�Ƃ��O��ł�����
�@�@�\�����̃t���C�g�́A�_�o�ǂ̌����͗c�����ł̑�l�̐��I�U�f���Ǝ咣���Ă������͓��I�v�����ւƏC������
�@�@�@�\�G�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X�͌l�𗝉����钆�j�I�T�O�Ƃ��čŌ�܂ŕێ����ꂽ
�@�@�@�\�{�\�I�Ȑ����I�G�l���M�[(���r�h�[)�Ǝ���Ƃ̊��������_�o�ǂ̌����ƌ��Ȃ��ꂽ
�@���_���͗Ö@�̌���(�S�I���u�_)
�@�\�S���G�X(�C�h)�A����(�G�S)�A������(�X�[�p�[�G�S)��3�̈�ɕ����A���̑��ݍ�p����S�̓����𑨂���
�@�@�\���ꂼ�ꂪ�������ē����Ă���(�\���_)
�@�@�G�X(Es); �����w�I�Ȗ{�\�Ɋ�Â������I�Œ��ړI�ȏ[���悤�Ƃ���S�̓���
�@�@�@�\�G�X����߂Ă����Ԃ͎����O�ӎ��̂�����͂邩�ɑ傫��
�@�@������(Super Ego); ���e�𒆐S�Ƃ����Љ�K�͂��l�ɑg�ݍ��܂ꂽ���̂Ŏ���̊Ď���
�@�@�@�\�N���ɂ͂��̒����䂪�������Ď��䗝�z�ɂȂ�Ƃ���Ă���
�@�@����(Ego); �G�X����̗~���������߂Ɍ����̊��⒴����Ƃ̒�����}�铭��������
�@�@�@�\�O�E��m�o�����ȊT�O��킽�����ӎ��Ɋւ������
�@�@�@�\���䂪����������ۂɁA���܂��܂Ȗh�q�@�����p������
�@�@�@�@�\�G�X����̗~���⒴���䂪��������ƁA��������ɂȂ�A��荂�x�ȐS����Ԃ��炻��ȑO�̏�Ԃɖ߂�u�ލs�v��������
�@�@�@�@�@�\�p�ɂɋN����ƁA���ꂪ���s����Ǐ�Ƃ��Č�����
�@���_���͗Ö@�̃v���Z�X
�@�\���Î҂͒�����ۂ��u�����ɕY�����Ӂv���ێ����Ĕ핪�͎҂Ɏ��R�A�z�����߂�
�@�@�\�핪�͎҂́A�L���⊋���Ȃǂ����t�ŘA�z�������ɍs���Ŏ������Ƃ�����(�s����)
�@�\�핪�͎҂́A����̖��E�Ǐ���������A���ȗ�����[�߂����Ƃ���Ă������A�ӎ�����W�Q����t���I���ۂ�������(��R)
�@�@e.g., ���ӎ��̊����̓��@�ɖ𗧂A�z�̋��ہA���Â֔�������l�X�Ȍ���etc�c�c
�@�@�\���̌��ۂ͒P�Ȃ�������ׂ���Q���ł͂Ȃ�
�@�@�@�\�G�X�ƒ�����A������\���_�I�ɑ�����l�����Ɍq����A���_���͂̎��ËZ�@�Ɨ��_�ւ̔��W�ɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă���
�@�@�\���_���͎��Ò��̒�R�̒��ŁA���ɏd�v�Ȃ͓̂]�ڂɌ��ѕt�����u�]�ڒ�R�v
�@�@�@�\�]�ڂƂ́A�ߋ��̏d�v�Ȑl���Ƃ̊W�ő̌����ꂽ�����s�����A���݂̑ΐl�W�⎡�Î҂Ƃ̊W�ōČ�����邱��
�@�@�@�@�\�]�ڂ́A���_���͓��L�̗c�����ւ̑R�𑣐i����\���Ō����ɂȂ�
�@�@�@�@�\�c�����̊��������݂̎��Îҁ\�핪�͎ҊW�̒��ōĔR���ē]�ڐ_�o�ǂ�������
�@�@�@�@�@�\�]�ڂƓ]�ڐ_�o�ǂ́A�l�H�I�Ȏ��ԁE�a�C�ł����āA������_�Ŏ��Î҂���̓����������₷��(Freud, 1914)
�@�@�@�@�@�\���Î҂͔핪�͎҂��]�ڂ̒��Ŏ����l�X�Ȍ����������I�ɌJ��Ԃ����̂�j�~���A�����A�z�̂��߂̘b��Ƃ���
�@�@�@�@�@�@�\��R�����߂���A����L�����z�N����ď��߂āA�}�����ꂽ�ϔO������Ɏ�����A�S���đg�D�������
�@�@�@�@�@�@�@�\���̎��ÓI�ω��������炷�܂Ōp������镪�͍�Ƃ��u�O�ꑀ��v�Ƃ���
�h�q�@��(Defence Mechanisms)
�@�\���䂪�����ɓK�����邽�ߕs�������ˑ��~���ɑ��Ė��ӎ��ɓ�������@��
�@�@�\��\�I�ȕ��Ƃ��Ĉȉ��̂悤�Ȃ��̂�����
�@�@1. �}��(Repression); �ア�������邽�߂ɑ�ڂɌ���
�@�@�@�\�q�X�e���[�Ǐ�͗}�����ꂽ���I�Փ��̕ό`
�@�@2. �۔F(Denial); �s���̈����s�����Ȍ��������₷�邱��
�@�@�@�\�}���ƃZ�b�g�ɂȂ��ē����₷��
�@�@3. �ێ�(Introjection); ������邱�ƁB�u�C�ɓ���v�u�H���Ă�����v�u�ۂ�ł�����v�Ȃ�
�@�@4. ���ꉻ(Identification); ����ƈ�̉����邱�Ƃ����A�Γ��̊W�ł͂Ȃ���ɃA�����B�o�����X��L����
�@�@�@�\���I���ꐫ�̊l���ɏd�v�ȐS�I�@��
�@�@�@�\����`�ɍU���҂Ƃ̓��ꉻ������
�@�@5. �u��(Isolation); �s���Ə�̗��҂̊W���₽��A�ϔO�������ӎ��ɂ̂ڂ邪�A����͎��o����Ȃ�����
�@�@6. �m����(Intellectualization); �m�I���������ŁA�����E������������Ȃ�����
�@�@�@�\�v�t���ɂ����鐫�Փ��̑Ώ����Y��
�@�@7. ������(Rationalization); �������E�k�قŐ��������邾���Ŏ��ۂ͔F�߂Ă��Ȃ�����
�@�@8. �����`��(Reaction Formation); �}�����ꂽ�Փ��Ɛ����̌X���ł���ɕ⋭�H������邱��
�@�@9. ����(Undoing); �u�����ꂽ�������ɑł������E��蒼�����߂ɓ���
�@�@�@�\�����_�o�ǂɌ����ɂ݂���
�@�@10. �u������(Replacement); �~���E�Ώۂ𑼂ɒu�������邱��
�@�@11. ���ˁA���e(Projection); ���Ȃ̐[���Ȋ���E�~���𑼐l�E�O�I���ۂ̂����ɂ���ӔC�]��
�@�@12. �ލs(Regression); �ߋ��̔��B�i�K�E���n�ȏ�Ԃɖ߂�A�����Ŗ����悤�Ƃ��鎖
�@�@13. ����(Sublimation); �{�\�Փ������I������U���ȊO�̖ړI�ɐU��������邱�ƂŁA�|�p�ȂǎЉ�I�ɐ��������h�q
�@�@14. ���e���ꉻ(Projective Identification); ����Ɛ[������Ă���Ɗ����A�v�����݂��������邱��
�@�@�@�\�����Ƌ��ʂ���_�����邪�A�א��ɋ߂�
�S��(���_)�\���I���B���_(�Q���I���B�_)
�@�\���_���͗��_�̓����̓��r�h�[�̒i�K�I���B�Ɗ֘A���Đ��_�����B���Ă����ߒ����l�@���邱��
�@�@1. ���O��(Oral Stage); �������̏����œ����z�������𒆊j�Ƃ��ĐS�g�����B���鎞��(����1�N�����炢�܂�)
�@�@�@�\���̎��A��e�Ƃ́u��{�I�ȐM�����v�����N�Ȏ���̊�b�ƂȂ�
�@�@�@�\���S�Ȏ��Ȉ��͈ˑ��~���̖����ƍ������_�@�Ƃ��Đ�����
�@�@2. ����(Anal Stage); ���E�A������̐_�o�x�z���������召�ւ̂������n�܂鎞��(����8�����`3�C4��)
�@�@�@�\�����E�r���̐����I������������Љ�K�ɏ]���s������������
�@�@�@�@�\��������Ύ����E�ւ肪���܂�A���s����Δ��R�E�^�f���萶����
�@�@�@�@�\�߈����̔����Ɗ֘A������Ƃ����
�@�@3. �j����(Phallic Stage); ���̋�ʂɖڊo�߂鎞��(3�A4�`6�A7����)
�@�@�@�\�����̐e�ւ̓G�ӂƈِ��̐e�ւ̐��I����������(�G�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X)
�@�@�@�\���̎����ɓ��L�Ȓj���̐S��
�@�@�@�@�\�����s��; �G�f�B�v�X��]��}�����鋰�|�S �� �j�q�ɂ�����哱���r���̋��|
�@�@�@�@�\�j����]; ���q�ɂ�����哱���ւ̑A�]
�@�@4. ������(Latency Period); �G�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X���}������A�����̐e�֓��ꉻ���i��(5�`12����)
�@�@�@�\���I���n����������܂Ő��I���B�������݂��鎞��
�@�@5. �����(Genital Stage); ����̐l�i�̓Ɨ������`�����鎞�� �� ���䓯�ꐫ(Ego Identity)(�v�t���E�N���ȍ~)
�@�@�@�\���䓯�ꐫ�͐N���ɒB�����ׂ����S�I�ۑ�
�@�@�@�@�\�ߋ��A���݁A�����̎������A�Љ�y�ю������g���F�ߊ��҂�����̂��ׂĂ�����т��鎩�������グ��
���p����: �S���w���� ��{�L�[���[�h �A�Տ��S���w�L�[���[�h (�L��t�o���\KEYWORD SERIES)
�A�Տ��S���w�L�[���[�h (�L��t�o���\KEYWORD SERIES) �A�Տ��S���w�Ƃ͉����낤���\��{���w�сA�l����
�A�Տ��S���w�Ƃ͉����낤���\��{���w�сA�l����
Keyword: ���_���͗Ö@�A���R�A�z�@�A���ӎ��A���@�A�G�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X�A���r�h�[�A�G�X�A����A������A�ލs�A�]�ځA�]�ڒ�R�A�O�ꑀ��A�h�q�@���A�Q���I���B�_�A���O���A�����A�j�����A�������A�����
���k�Ғ��S�Ö@�Ƃ́H
�@�\���W���[�Y(Rogers, C.R)�ɂ���đn�n����A�[���E���W���Ă����J�E���Z�����O���_
�@�\��w���I�J�E���Z�����O�� ���k�Ғ��S�Ö@�� �p�[�\���Z���^�[�h�E�A�v���[�`�Ɩ��̂��ω����Ă���
�@�@�\���̂̕ω��ɂ��ւ�炸�ȉ��̂悤�ȂR�̊�{�������ێ����ꑱ���Ă���(Rogers, 1986)
�@�@1. �l�ɂ͖{���A���Ȏ����ւ̗͂����݂��Ă���(���W���[�Y�̑�O��)
�@�@2. ���̌l���A���鑣�i�I�ȐS���I���y�ɎN�����Ƃ�(�l�i�ϗe�̕K�v�\���̌���)
�@�@3. ���̌l�ɂ͌��ݓI�Ȑl�i�ϗe���N����(�\���ɋ@�\����l�Ԃ̌���)
�@���ȗ��_
�@�\���W���[�Y�̗��_�͎��ȗ��_�ƌĂ��
�@�@�\�l�Ԃ�L�@�̂Ƃ��đ����A���̗L�@�̂͐�V�I�X���Ƃ��āu�����X���v�����Ɖ��肵��
�@�@�\�q�ϓI�ɂǂ̂悤�ł��邩�����A�ǂ̂悤�Ɏ���Ă��邩�Ƃ������Ƃ��{���Ƃ���
�@�@�@�\���Ȃ��ǂ̂悤�ɔF�����Ă��邩�Ƃ����u���ȊT�O�v���d�v
�@�@�@�@�\�u�̌��v����Ă��鎩�Ȃ̗L��l�ƃY����Εs�K���ɂȂ�A��v�x�������Ȃ�u���Ȉ�v�v�����K���I���
�@���k�Ғ��S�Ö@�̓���
�@�\�l�Ԃ͐l�i�ϗe��ړI�Ƃ��邱�ƂŁA�Ƃ�����Ƌ����I�E�Њd�I�ԓx�Őڂ��鎖��������
�@�@�\���ݓI�Ȑl�i�ϗe���\�ɂ���S���I���y�͍��o���Ȃ�
�@�@�@�\�l�̎��R�Ȏ��ȒT������������A����̌o���ɖڂ�����܂܊O�E�ɑΏ����邱�ƂɂȂ邽��
�@�\���W���[�Y�́A���R�ŋ��ق̖����A���S�ȐS���I���y�������ݓI�l�i�ϗe�ɂƂ��ĕs���̏����Ƃ��ďd������
�@�@�\���̏��������J�E���Z���[�̑ԓx�Ƃ��āA3�̑ԓx������ݒ肵��(Rogers, 1957)
�@�@�@1. �������̍m��I�z��(Unconditional Positive Regard)
�@�@�@2. ���Ȉ�v���邢�͏�����(Congruence or Genuineness)
�@�@�@3. �����I����(Empathic Understandng)
�@�@�@�@�\3�̑ԓx�����̂ق��Ɂu�v���[���X(Presence)�v�Ƃ����T�O�����Ă���(Rogers, 1986)
�@�@�@�@�\�ڍׂ́u�J�E���Z�����O�̊�{�I�ԓx�ƋZ�@�v�̍����Q��
�@�X��
�@�\�N���C�A���g�̑̌����Ă��鐢�E�Ɏ����X����s��
�@�@�\�J�E���Z���[�̌X���ɐG������A�N���C�G���g���������g�̐S�Ɏ����X����悤�ɂȂ�A�������g�ւ̐ڂ������ω�����
�@�@�@�\�������g�ւ̐ڂ����̕ω����A�N���C�G���g�̃p�[�\�i���e�B�ϗe�Ɍq����
���p����: �S���w���� ��{�L�[���[�h
Keyword: ���k�Ғ��S�Ö@�A���ȗ��_�A���ȊT�O�A�̌��A���Ȉ�v�A�������̍m��I�z���A�����I�����A�v���[���X�A�X��
�F�m�s���Ö@�Ƃ́H
�@�\�l�Ԃ̔F�m�A�s���A��A�����Ɋւ��������ÑΏۂƂ���A�v���[�`�̑���
�@�@�\�e���ʂ͑��݂ɉe����^�������Ƃ����O��̂��ƁA���ʓI�ɓ����������s���A�ϗe���N�����A���Ì��ʂ������o��
�@�@�\�w�K���_��s�����_�Ȃǂɂ�����S���w�̐��ʂ����p�����G�r�f���X�x�[�X�h�̐S���Ö@
�@�@�@�\�F�m�Ö@�A�_���Ö@�̂ق��ASST�A���ȋ����P���A�X�g���X�Ɖu�P���Ȃǎ��Ì��ʂ�������Ă��鎡�Ãp�b�P�[�W���܂�
�@�F�m�s���Ö@�̖ړI�ƓK�p
�@�\�N���C�G���g�Ƃ̊W�͋����I�ł���A�N���C�G���g�̃Z���t�R���g���[�����ŏI�ڕW�Ƃ���
�@�@�\��\�I�ȃA�v���[�`�͔F�m�Ö@�ƍs���Ö@�ł���A��������F�m�̕ϗe�����Â̕W�I�Ƃ��Ă���
�@�\���̔��W�ɂ�āA�}���Ǐ��S���I�X�g���X�����A�S���I�s�K���ȂǂɌ����Ă������ÑΏۂ��g�債�����Ă���
�@���̍\����
�@�@�\�F�m�s���Ö@�̓N���C�G���g�̕���������ȉ��̂悤�ɍ\��������������
�@�@�@1. �l�ԊW������̒��ɂ���l�X�Ȏ肪����ɖ�肪����ꍇ(���̖��)
�@�@�@2. �U�镑����ԓx�A�s���ɖ�肪������ꍇ(�s���̖��)
�@�@�@3. �l�����A�l�����̃X�^�C���ɖ�肪������ꍇ(�F�m�̖��)
�@�@�@4. ����A��ʂł̖��(��̖��)
�@�@�@5. �g�̓I�Ǐ�ɖ��݂̂���ꍇ(�g�̖̂��)
�@�@�@6. �����A�S�A���@�Â��ɖ��݂̂���ꍇ(���@�Â��̖��)
�@�@�@�\�������ꂽ�i�������Â̕W�I�Ƃ��Ė��m������
�@�@�@�\���������āA���ÕW�I�̂ǂ�����������ɂ����邩�����������
�@�@�@�@�\���������₷���Ƃ��납��ς��Ă������Ƃ���
�@�F�m�s���Ö@�̓K�p
�@�\�F�m�s���Ö@�́A�ȉ��̂悤�ȏ�ʁA�Ǐ�ɑ��đ傫�Ȏ��Ì��ʂ��F�߂��Ă���
�@�@�\�C����Q�A�}���A�S�ʐ��s����Q�A���|���̏�Q�A��������Q�A�}���̃X�g���X��Q�A�O����X�g���X��Q�A�ېH��Q�A
�@�@�@�u�ɁA�A���R�[�����p�A�w�����k�A���A�a�Ȃǂ̐����K���a�Ƃ����������������҂̌��N�s���̌`��
�F�m�Ö@
�@�\�x�b�N�ɂ���ĊJ�����ꂽ
�@�@�\�N���C�G���g�̍l�����̃X�^�C��(�F�m)�����Â̕W�I�Ƃ��A���̕ϗe��ʂ��āA��A�s���ʂ̖��̉�����}�鎡�Ö@
�@�\�F�m�s���Ö@�Ƒ��̂����̈�Q�̎��ÃA�v���[�`�̑�\�I�Ȃ���
�@�x�b�N�̔F�m�Ö@(Beck, A.T.)�̃v���Z�X
�@�@�\�N���C�G���g�̔ے�I�ŔߊϓI�ȁA�F�m�̘c�݂��C�����āA�����I�œK���I�ȔF�m�ɕϗe������Ö@
�@�@�@�\�F�m�̘c�݂́A�u�����v�l�v�Ɓu�X�L�[�}�v�Ƃ���2�̃��x���Ɍ����
�@�@�@�@�����v�l
�@�@�@�@�@�\�������̏�ʂɂ����ďu�ԓI�ɓ��̒��ɕ�����ł���l����C���[�W
�@�@�@�@�@�@�\���ӂ�������Ηe�ՂɈӎ������\
�@�@�@�@�X�L�[�}
�@�@�@�@�@�\�����v�l�̔w�i�ɂ��鉿�l�ς�l���ς̂悤�Ȃ��̂ŁA�l�Ԃ̍l�����ɓ���̘g�g�݂�^�������
�@�@�F�m�Ö@�̃v���Z�X
�@�@�@1. ���m��������ŁA�����v�l�ɒ��ӂ������A����A��������
�@�@�@2. �����v�l�̒��Ɉ��̃p�^�[�������o�����Ƃɂ���ăX�L�[�}��A��������
�@�@�@�@�\�F�m����茻���œK���I�Ȃ��̂ɏC�����Ă������ƂŁA�N���C�G���g�̏�Ԃ�K���I�ɕω������Ă���
�@�@�@�@�\10�`20�炢�̒Z���I�Ȏ��ÂɂȂ邱�Ƃ�����
�@�@�F�m�Ö@�̓K�p
�@�@�@�\���a�ƃp�j�b�N��Q���ł����ӂƂ���
�@�@�@�\�ېH��Q��p�[�\�i���e�B��Q�Ȃǂɂ��K�p�����
�_���Ö@(Ellis, A.)
�@�@�\�l�Ԃ̔����͎h���ɂ���Ăł͂Ȃ��A�h�����ǂ��~�߂����Ƃ����F�m�ɂ���Đ�����Ƃ����l�����ɗ��r
�@�@�@�\�l�Ԃ̔F�m��ω�������Δ������ω�����Ƃ����l�����́A�x�b�N�̔F�m�Ö@�Ƌ���
�@�@�@�\������Ö@�Ƃ����
�@�@�_���Ö@�̓���
�@�@�@�\��b���_�ł���ABC���_�ɏW���
�@�@�@�@1. �l�ԂɔY��(����(C))�������炷�̂́A�o����(A)�ł͂Ȃ��A�o�������ǂ��~�߂邩�Ƃ������ȐM�O(B)
�@�@�@�@�@�\���ȐM�O(Irrational Belief)�Ƃ́A���I�Ŕ��I�ȁA�N���C�G���g��s�K�ɂ���l����
�@�@�@�@2. ���ȐM�O���A�����I�ȐM�O(Rattional Belief)�ɕς��邱�ƂŁA�N���C�A���g�̔Y��(C)�������ł���
�@�@�@�@�@�\�M�O�̕ύX�ɒ�R������ꍇ�́A�_���Ȃǂ̕��@���s���A���ۂ̏�ʂō����I�M�O��K�p����h����s�킹��
�@�S���I�X�g���X���_(Lazarus, R. S. et al.)
�@�@�\���Ɛl�Ԃ����݂ɉe�����y�ڂ������A���̃v���Z�X�����������Ă����Ԃ������X�g���X
�@�@�@�\�X�g���X�̓X�g���b�T�\�ɂ���Ĉ�����I�Ɉ����N�������̂ł͂Ȃ�
�@�@�F�m�I�]���ƃR�[�s���O
�@�@�@�\�X�g���X�����́A�X�g���b�T�\�̋���ł͂Ȃ��A�F�m�I�]���ƃR�[�s���O�ɂ���Č��肳���
�@�@�@�@1. �Ȃ�炩�̃X�g���b�T�\���o�������ꍇ�ɁA���̌o���̋�������A������ǂ̂悤�ɑ����邩(�F�m�I�]��)
�@�@�@�@�@�\�ꎞ�I�]���ƓI�]��������
�@�@�@�@�@�@�\�ꎞ�I�]���Ƃ́A�o�����������ɂƂ��ėL�Q���ǂ����f����X�g���b�T�\���̂ɑ���]��
�@�@�@�@�@�@�\�I�]���Ƃ́A�X�g���b�T�\�ɑ��Ăǂ̂悤�ȑΏ����\���Ƃ����R�[�s���O�ɑ���]��
�@�@�@�@2. �X�g���X������ጸ�����邽�߂̑Ώ�(�R�[�s���O)
�@�@�@�@�@�\���œ_�^�Ə�v�_�^�̃R�[�s���O������
�@�@�@�@�@�@�\�X�g���X�����������炷�X�g���b�T�\�ɑ��čs�������(���œ_�^)
�@�@�@�@�@�@�\�X�g���X�����ɑ��čs�������(��œ_�^)
�@�X�g���X�}�l�W�����g
�@�@�\�X�g���X������ጸ��������A�ߓx�̃X�g���X������\�o�����Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����������
�@�@�@�\�X�g���X�}�l�W�����g�̏d�v�ȍ\���v�f
�@�@�@1. �h���ƂȂ���ւ̉��(�X�g���b�T�\�̌y���A����)
�@�@�@2. �l�̔F�m�ւ̉��(�h���̑������A�l�����̕ϗe)
�@�@�@3. �l�̃R�[�s���O�ւ̉��(�Ώ����p�[�g���[�̊g�[�ASST)
�@�@�@4. �l�̃X�g���X�����ւ̉��(�����N�Z�[�V�����@��p���A�S�g�̃X�g���X�������������g�Ŋɘa)
�e�s���Ö@�̗��_�ƃv���Z�X
�@�\�����I�ɖ��炩�ɂ���Ă���w�K���_�A�s�����_�Ɋ�Â��Đl�Ԃ̖��s����ϗe��������@
�@�@�\�l�Ԃ̖��s���́A�K�ȍs���̊w�K���s�����Ă��錋�ʁA���邢�͕s�K�ȍs�����w�K�������ʂł���Ƃ���
�@�@�\�K�ȍs���̊w�K���s�����A�w�K���ꂽ�s�K�ȍs������������Ƃ����`�ōs���̕ϗe��ڎw��
�@�@�@�\���̐S���Ö@�Ɣ�r���āA�q�ϐ��ƕ��Ր��������u�����Ă���
�@�s���Ö@�̓���
�@�@1. �s�����_����b�����Ƃ���
�@�@2�D���Â̖ڕW�m�ɂ��A�q�ϓI�����䂪�\�ȍs���݂̂����ÑΏۂƂ���
�@�@3. �Ǐ��s�K���s���̊w�K���邢�͓K���s�����݊w�K�Ƃ��ĂƂ炦��
�@�@4. ���Â̏œ_���ߋ��ł͂Ȃ������݂ɂ��Ă�
�@�@5. ���Â̍ŏI�ڕW���s���̃Z���t�R���g���[���Ƃ���
�@�@6. ���̐S���Ö@�Ɣ�r���Ď��Âɗv���鎞�Ԃ��Z���A�o�߂��q�ϓI�ɗ����ł���
�@�w�K��3�^�C�v
�@�@1. ���X�|���f���g�����Â��ɂ��ϗe
�@�@�@�\�����N�Z�[�V�����@���w�K�����邱�Ƃɂ���āA�s���⋰�|�Ȃǂ̕s�K�Ȕ�����}������(�t�}�~)
�@�@�@�@�\�t�}�~�̌��������p���āA�E�H���s(Wolpe, 1958)���J�������̂��n���I�E����@
�@�@�@�@�@�\�n���I�E����@�Ƃ́A�s���⋰�|�������N���������h���ɑ���ߏ�Ȋ����n���I�Ɏ�߂Ă����A
�@�@�@�@�@�@�ŏI�I�ɏ����h���ɑ��锽�����{��Ȃ��悤�ɂ�����@
�@�@�@�\�����ɕs�����y�����邱�Ƃ��\�ȃG�N�X�|�[�W���[(�\�I�@)���p������P�[�X�������Ă���
�@�@�@�@�\�s���⋰�|�������N�����h���Ɋ��҂����炷���Ƃɂ���āA�h���ɑ���s�K���I�Ȕ������������鎡��
�@�@�@�@�\���ۂ̎h����p������@�ƁA�C���[�W��p������@������
�@�@�@�@�\�s���⋰�|�������N������Ȃ��Ȃ�܂ŁA�h����^�������邱�Ƃ��K�v
�@�@2. �I�y�����g�����Â��ɂ��ϗe
�@�@�@�\�I�y�����g�����Â������p�����Z�@�Ƃ��āA�g�[�N���G�R�m�~�[�A�V�F�C�s���O�Ȃǂ�����
�@�@�@�g�[�N���G�R�m�~�[
�@�@�@�@�\���̉ۑ�𐳂������s�ł������A���������ɏ]���ăg�[�N�����V�Ƃ��ė^���A�s��������������@
�@�@�@�@�@���g�[�N���Ƃ́A�V�[����J�[�h�ȂǁA���ʂɒB����Ȃ�炩�̕�V�ƌ����ł����p�ݕ�
�@�@�@�@�@�\���Ï�ʂł͈�ʂɃV�F�C�s���O�Ƃ̕��p�����ʓI�Ƃ����
�@�@�@�V�F�C�s���O�́A���̖ڕW�s���Ɏ���܂ł̃v���Z�X��i�K�I�ɐݒ肵�A��������𐋍s�����Ă������@
�@�@�@�@�\�X���[���X�e�b�v�̌����Ƃ��Ă��
�@�@3. �Љ�I�w�K�ɂ��ϗe
�@�@�@�\���s���̕ϗe�ɂ������āA�F�m�I�������d��������̂ŁA���f�����O(�ώ@�w�K)�ƌĂ��
�@�@�@�@�\�o���f���[���́A���ɑΐl�W�̏�ʂŁA���҂̍s���̊ώ@���V�����s���̏K���Ɍq���邱�Ƃ�����
�@�@�@�@�\���f�����O�́A�������g�����Ȃ��Ƃ�����ʂɂ��Ȃ��Ƃ��A�����ɂ��鑼�҂̍s�����ώ@���邱�ƂŐ�������
�@�@�@�@�\�Տ���ʂɂ����āA���s���̕ϗe�⎡�Âɗ��p����ꍇ�́A���f�����O�@(���f�����O�Ö@)�ƌĂ�
�@�\�[�V�����E�X�L���E�g���[�j���O(Social Skill Training: SST)
�@�@�\�ΐl�W���\�z���A������ێ����邽�߂ɕK�v�ȍs�����K�����邽�߂̃g���[�j���O
�@�@�\�ΐl�s����ɖ�肪����ꍇ�A���̌������Љ�I�X�L���̌��@�Ƃ��čl����
�@�@�@�\�K�v�ȎЉ�I�X�L�����w�K���Ȃ���A�s�K�ȍs�����C�����A�ΐl�s����̖������P���悤�Ƃ��鎡�ËZ�@
�@�@�@SST�̃v���Z�X
�@�@�@�@1. ����; �w�K���ׂ��X�L������肵����ŁA�X�L���̊T�O��SST�̈Ӌ`�����
�@�@�@�@2. ���f�����O; �]�܂������f���̒�
�@�@�@�@3. �s�����n�[�T��; �X�L������K
�@�@�@�@4. �t�B�[�h�o�b�N; �K�ȍs���������A�C��
�@�@�@�@5. ���퐶����ʂւ̔ʉ�; �K�������X�L����������ʂŎ��H�ł��邩�ǂ����m�F
�@ �@SST�̓K�p
�@�@�@�\�������ݎv�Ă̎q�ǂ��A�U���I�Ȏq�ǂ��A�Ǘ������q���ɑ���SST
�@�@�@�\���������ǂ̌o�߂Ɠ]�A�ւ̗̍p�ɂ���āA�Ĕ��\�h�ւƂȂ���
�@�@�@�@�\���������NJ������҂̉Ƒ��ɂ�镉�̏�\�o�������ƍĔ������������߁A�Ƒ��̊��҂̊ւ�����SST�ɂ���ďC�����邱�Ƃ�
���p����:  �A�Տ��S���w�L�[���[�h (�L��t�o���\KEYWORD SERIES)
�A�Տ��S���w�L�[���[�h (�L��t�o���\KEYWORD SERIES) �A�S���w���� ��{�L�[���[�h
�A�S���w���� ��{�L�[���[�h
Keyword: �F�m�s���Ö@�A�F�m�Ö@�A�_���Ö@�A�S���I�X�g���X���_�A�X�g���X�}�l�W�����g�A�n���I�E����@�A�g�[�N���G�R�m�~�[�A�V�F�C�s���O�A���f�����O�A�\�[�V�����E�X�L���E�g���[�j���O
���̑��̐S���Ö@
�𗬕���(E. Berne)
�@�\�A�����J�̐��_�Ȉ�E.�o�[�����J�������l�ԍs���Ɋւ��闝�_�̌n�Ƃ���Ɋ�Â����Ö@
�@�@�\�݂��ɔ����������Ă���l�X�̊Ԃōs���Ă���𗬂͂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���
�@�@�\�S�̍\����@�\���L����}�����g���ĕ�����₷����������Ƃ���ɓ���������
�@�\���_��͐��_���͂���o�����Ă���ʂ��������A���ӎ��̑��݂����肹���A�u���A�����Łv���d������
�@�@�\���ȕ��͂ƏW�c�Ö@�������Ƃ��A�l�Ԑ��S���w�̒��Ɉʒu�Â�����
�@�@�\�Z�@�ʂ���͐��_���͂����F�m�s���Ö@�Ƌ��ʂ�����̂�����
�@4�̕���
�@�@�\�𗬕��͂ōs����4�̕���
�@�@�@1. �\������
�@�@�@�\�p�[�\�i���e�B��e(P)�A��l(A)�A�q�ǂ�(C)��3�̎����Ԃ�����Ƒz��
�@�@�@�@�\�ɂ��A�e�l�ɂ��D�ʂƂȂ鎩���Ԃ��قȂ�ƍl������
�@�@�@2. �𗬃p�^�[������
�@�@�@�\2�l�̊Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����̗l�q��P�AA�AC�Ԃ̃x�N�g���ŕ���
�@�@�@3. �Q�[������
�@�@�@�\���z�Ɋׂ����ΐl�W�̃p�^�[����
�@�@�@4. �r�{����
�@�@�@�\�l�������I�ɏ]���Ă��܂��l���́u�r�{�v�̕���
�@�@�@�@�\���̓��e��m��A������u���A�����Łv���������錈�f�����A�V�����l������݂������Ƃ��𗬕��͂̍ŏI�ړI
�@�𗬕��͂̓K�p
�@�@�\�S�g�ǁA�_�o�ǁA���a�ȂǑΐl�W�X�g���X�����̔��˂�o�߂Ɋ֗^����a�Ԃɑ��čL���p������
�@�@�@�\�P�Ƃ����Ö@�⑼�̌l�Ö@�ƕ��p����邱�Ƃ�����
�@�@�\�G�S�O�����ɂ�鎩�ȗ����́A�E��̃����^���w���X�ȂǁA����҂̌��N����ɂ��L���K�p�����
�W�c���_�Ö@�E�T�C�R�h���}
�@�\�L�`�ɂ́A�����ʂ�W�c��Ώۂɂ������_�Ö@
�@�@�\���`�ɂ́A�W�c�̑��ݍ�p��ʂ��Đ����̐l�i�A���s���A�ΐl�W�̉��P����}�邽�߂ɈӐ}�I�ɑg�D���ꂽ�W�c�̐S���Ö@
�@�@�\���ݍ�p�͎�Ɍ���ɂ���ĂȂ����
�@�\���W�c�ɂ�鎡�Ẫ��J�j�Y���A�Z�@�A�v���Z�X�Ȃǂ����肳��A����Ɋ�Â������ÖړI����j�����Ă���
�@�\���_���͓I�ȗ���ɗ��������̂��w�����Ƃ��������A���̂ق��ɂ������̗��ꂪ����
�@�@�\��\�I�ȋZ�@�Ƃ��ĐS����������
�@�S�����E�T�C�R�h���}(J.Moreno)
�@�@�\����������̂Ƃ����W�c�S���Ö@��1��
�@�@�@�\�u�������v�Ɓu�������Z�v��2�̌������d�������
�@�@�@�@�\�؏����Ō��܂������������̂ł͂Ȃ��A�u�������Łv�������e�[�}�̏Ɋ�Â���������������
�@�@�@�\���Â̏�ɕK�v�ȗv�f�͎厡�Î҂ł���ēA���Â̔}��ƂȂ�⏕����A�펡�Î҂ł��鉉�ҁA���҂Ƃ��Ȃ�ϋq�A����
�@�@�S�����̎菇
�@�@�@1. �ȒP�ȃE�H�[�~���O�A�b�v
�@�@�@2. ���ۂ̃h���}�̒i�K
�@�@�@�@�\�������̌����A��ʍ\�����s���ĉ��Z�ɓ���
�@�@�@�@�@�\����̕��g�������u�_�u���v�⑊��̗��ꂩ�玩��������u���������v�A�⏕����⑼�҂������鎩��������u�~���[�v�Ȃ�
�@�@�@3. �V�F�A�����O
�@�@�@�@�\����̑̌����������A���ꂼ��̑̌���b�������i�K
�X�g���X�Ɖu�P��(Stress Inoculation Training)Meichenbaum, 1977
�@�\�����w�ɂ�����Ɖu�̊T�O�������ꂽ�X�g���X�E���f�����x�[�X�Ƃ������Ö@
�@�@�\���O�Ɍy�߂̃X�g���b�T�\�ɂ��炳��A��肭����o���������Ȃ�A�������߂̃X�g���b�T�\�ɏo���킵�Ă��Ώ��ł���Ƒz��
�@�P����3�̒i�K
�@�@1. ����I�i�K
�@�@�@�\���Î҂ƃN���C�G���g���X�g���X���ɂ��ċ��ʗ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���
�@�@�@�@�\�X�g���X�����̔�������ߒ������ՂȌ��t�Ő��������
�@�@2. ���n�[�T���i�K
�@�@�@�\��̓I�ȃX�g���X�Ώ��X�L�����l������
�@�@�@�@�\�X�g���b�T�\�Ɋւ���m���𑝂₵�Ďv�����݂���߂����Ȃ�����
�@�@�@�@�@�\�X�g���b�T�\�Ɋւ��铦�������������ăX�g���b�T�\�ɒ��ʂ��鋰�|�S��ጸ
�@�@�@�@�@�\�g�̓I�����N�Z�[�V�����ɂ���Đ����I�o����ቺ������
�@�@�@�@�@�\�F�m�I�Ώ��X�L���Ƃ��ẮA�u�X�g���b�T�\�ɔ����Ă���Ƃ��v�Ȃǂɗp���鎩�Ȓq��p�ӂ��A���n�[�T�����s��
�@�@3. �w�K���ꂽ�Ώ��X�L���̎��s�i�K
�@�@�@�\�X�g���b�T�\�ɎN���ꂽ�ŁA�Ώ��X�L�����g�p���A�����ɂƂ��Č��ʂ���X�g���X�Ώ����@���N���C�G���g���g�����炩�ɂ���
�������Ö@(Problem Solving Therapy)D'Zurilla & Nezu, 1982
�@�\���퐶���̒��ł̖������\�͂����߁A���Ȍ��͊����������邱�ƂŐS�̖��̉�����}�鎡�Ö@
�@�@�\�l�������̖����ǂ̂悤�ɗ������邩�ɂ���ĕs����}���C����������Ƒz��
�@�@�@�\���ɁA��肻�̂��̂̑������A�����A���̎d���A���А���Ώ��\���ɑ���]���A�������Ƃ������l�̔F�m���e��
�@�������̕��@���w�Ԏ��Ö@
�@�@�\�Y�����ƃl�Y�ɂ���đ̌n�����ꂽ���Ö@�ŁA�ȉ���5�̒i�K���o�āA���Â�ڎw��
�@�@�@1. �������ƂȂ��Ă��邩�𖾂炩�ɂ���i�K(Problem Orientation)
�@�@�@2. ����]������i�K(Problem Definition and Formulation)
�@�@�@3. ���l�Ȗ��������@�̌���(Generation of Alternatives)
�@�@�@4. �����\�ȉ������@��T������i�K(Decision Making)
�@�@�@5. ���������@�����s�����ʂ��m�F����i�K(Solution Implementation and Vertification)
�@�@�@�\5�̒i�K���o�邱�ƂŁA�N���C�G���g���������g�Ŗ������ł���Ƃ������Ȍ��͊�������A�Z���t�R���g���[���ł���悤�ɂ���
�@�������Ö@�̓K�p
�@�@�\�P�ɐ��̂��a�A�L�ꋰ�|���p�j�b�N��Q�A�O����X�g���X��Q�A�p�[�\�i���e�B��Q�A�얞���ÁA�����u�ɁA
�@�@�@���@�\�s�S�A�v�w�Ԋ����A�Տ��I�ȃX�g���X�Ǘ��Ȃǂ̖��ɓK�p�����
�ΐl�W�Ö@(Interpersonal Therapy:IPT)Klerman, Weissman
�@�\��o�Ȍ^�E�_�a���̂��a�ɑ��鐸�_�Ö@
�@�@�\���a�̔��ǂ�o�߁A�ɑ��Đ����w�I�ȐƎ㐫�ɉ������҂�������ΐl�W��̖�肪�e����^����Ƃ�������������
�@�@�\���ۂ̎��Âŗc�����̑̌���h�q�@���⊋���Ȃǂ����グ�邱�Ƃ͂��Ȃ�
�@�@�\���҂����ݕ������̓I�Ȗ�肪�d�������
�@�\���_�I�ɂ͐��_���͂̑ΐl�W�w�h�̗���������Ă���
�@�@�\���Â̖ړI�͋�̓I�ŁA�Z�@�͍s���Ö@�̉e�����Ă���
�@�@����
�@�@�\�ΐl�W�Ö@���ꕔ�̑傤�a����Q�̎��ÂɌ��ʓI�ł��邱�Ƃ�������Ă���
�@�@�i�ߕ�
�@�@�\���Â̓p�b�P�[�W�����ꂽ�}�j���A����p���A�ʏ�A�Ö@�ƕ��p����
�@�@�\���45�����x�̖ʐڂ�12�`16�T�ԍs��
�@�@�@1. �ŏ���3�Z�b�V����
�@�@�@�\�f�f�Ƒΐl�W�̖��A���ɂ��a�G�s�\�[�h�̔��ǎ����ɋN�������ΐl�W�̕ω��𖾂炩�ɂ���
�@�@�@2. ���Ԋ�
�@�@�@�\�ŏ��̃Z�b�V�����Ŗ��炩�ɂȂ����ΐl�W��̖��ɍ��킹�A�V�����ΐl�����A�ΐl�Z�p�̉��P�A��������������F�m��ς���
�@�@�@3. �Ō�̐���̃Z�b�V����
�@�@�@�\���Âɂ���ē������̂��m���Ȃ��̂ɂ���A�������G�s�\�[�h���Ĕ������ꍇ�̑Ώ��@�Ȃǂ��ڕW
�����P���@(Autogenic Training: AT)Schultz, 1932
�@�\�S�g�̃����b�N�X����S�g�̌��N��ڎw�����Ö@
�@�@�\�u�C���������������Ă���v�Ƃ����Î����̒��Ŗ��S�ɌJ��Ԃ����Ƃɂ���āA�S�g�̒o�ɏ�Ԃ����o�����@
�@�\�ړI�͐S�g�̋@�\�̍Ē��������A�S�́u�đ̐����v�𑪂邱��
�@�@�\�����_�o�n�̉ߏ苻���𒾐Â��A�]�����̋@�\�����āA�S�g�̋@�\���z���I�X�^�V�X��Ԃɓ����S�������I���Ö@
�@�@�W�����K(Standard Exercise)
�@�@�\AT�̊�{�͕W�����K�ɂ���A1�̔w�i����(�S�ʓI���Ê�)��6�̌���(�����I����)����Ȃ�
�@�@�@�\�W�����K�̊e����
�@�@�@�@1�D�l���d�����K
�@�@�@�@2. �l���������K
�@�@�@�@3. �S���������K
�@�@�@�@4. �ċz�������K
�@�@�@�@5. �����������K
�@�@�@�@6. �z���������K
�@�@�@�@�\�W�����K�́A�C�X�Ȃǂɍ��|�����p���Ń����b�N�X���A���������ɏ����Ȃ���g�̋@�\�̒������s���Ă���
�@�@�@�@�\�g�̕��ʂ������A�ϋɓI�ɒ��ӂ������ĕω����N�����̂ł͂Ȃ��A�g�̕��ʂ̕ω��ɋC�Â��Ƃ����g�I�ԓx���d�v
�@�@�����P���@�̐S���w�I����
�@�@�\�Z���I����
�@�@�@1. �ْ���s���̌���
�@�@�@2. �{���}�����̌���
�@�@�@3. ���C��u�����̑���
�@�@�\�����I����
�@�@�@1. �S�g�̕ω��ւ̋C�Â��̑���
�@�@�@2. �ΐl�W�̈���
�@�@�@3. �X�g���X�ϐ��̑���
�@�@�@4. �����_�o�@�\�̈���
�@���K���K���Ȃ��l
�@�@�\�K�p���֊��Ȑl�X
�@�@�@�\�S�؍[�ǂⓝ�������ǂ̗z�����ҁA�ጌ������̉\���̂���l�A���A�a���҂Őg�̏Ǐ�̊Ď�������Ȑl
�@�@�\�K�p�ɒ��ӂ��K�v�Ȑl�X
�@�@�@�\�Γ��ኳ�҂�b��B�@�\���i�NJ��ҁA�����}����Ԃ������l
�@�@�@�\���K���Ɍ������㏸����ꍇ��AAT���s������ɕs�������傷��悤�Ȑl�ɂ����Ă��A�w���͐T�d�ɍs���K�v������
�o�C�I�t�B�[�h�o�b�N�ƃ����N�Z�[�V����
�@�\���̂̎�������@�\���j�������ɁA������s���|�C���g�Ɏ������Ö@�ƁA�S�g�̋@�\���߂���Ď������Ö@
�@�\���Ȃ̐��̌��ۂ��A�F�m�̗e�ՂȊO�����ɕϊ����ăt�B�[�h�o�b�N���A��������Ƃɐ��̌��ۂ����Ȑ��䂵�悤�Ƃ����@
�@�@���_�I�w�i
�@�@�\�ߑ�ȃX�g���X�ɂ���Ĉ����N�����ꂽ�S�g�ǂł́A�����I�Ȏ��Ȑ��䃁�J�j�Y�����j������������A�l�X�ȏǏ��悷��
�@�@�@�\�{�������[�v�ł��鎩������V�X�e���̈ꕔ���J�����A�蓮�I�ɃR���g���[�����Ă����@���L���ɂȂ�
�@�@�\�o�C�I�t�B�[�h�o�b�N��2�ʂ�̕��@
�@�@�@1. ���鐶�̔����ڈӐ}��������ɕω������悤�Ƃ��钼�ږ@
�@�@�@2. �ؓd�}�̒ቺ��畆���̏㏸��ʂ��āA�S�g�̃����N�Z�[�V�����悤�Ƃ���Ԑږ@
�@�@�����N�Z�[�V�����Ƃ�
�@�@�\���Ƃ��Ƃ́A�s����ْ��Ɲh�R����ؓ��̒o�ɂ��Ӗ����Ă���
�@�@�\���݂ł́A�X�g���X�Ƃ͑ɂɂ���S�g�̏�Ԃł���A�ȉ��̏�Ԃ��w��
�@�@�@1. �S�g���̌����_�o�����̒ቺ
�@�@�@2. �������_�o�����̘��i
�@�@�@3. �X�g���X�z�������̒ቺ
�@�@�@4. �Ɖu�@�\�̑���
�@�@�@�\�S�g�ǂɔF�߂��閝���̃X�g���X�E�ߋْ���Ԃ̎��Âɔ��ɗL��
�@�@�\��̓I�ȕ��@
�@�@�@1. �Q�i�I�ؒo�ɖ@
�@�@�@2. �Ԑږ@�ɂ��o�C�I�t�B�[�h�o�b�N
�@�@�@3. �����P���@
�@�@�@4. ���[�K
�@�@�@�\�o�C�I�t�B�[�h�o�b�N�͐��̂̎�������j����̃s���|�C���g�I�Ȏ��Ö@
�@�@�@�\�����N�Z�[�V�����͑S�g���̒��߂�_�������Ö@
�u���[�t�T�C�R�Z���s�[
�@�\�L�`�ɂ́A���Ê��Ԃ��Z���ł���Ȃ���A�����ʓI�Ō����I�Ȏ��Â�ڎw���S���Ö@
�@�@�\���҂̒��S�I�����ɏœ_�����킹�A�������d���A�Љ�K�����˂炤�ȈՐS���Ö@
�@�\���`�ɂ͐����I�Ȑ��_���͗Ö@�܂��āA���̔ᔻ�ƐV���ȓW�J�Ƃ��Đ����Ă�������
�@�@�\�l�i�̍č\���ł͂Ȃ��A�@���݂̏Ǐ��s�K����Ԃ̏����E���P�A�A�����̏�I�Ȗ��̗\�h�ɏœ_�����Ă��S���Ö@
�@�@�u���[�t�Z���s�[�̗��_
�@�@�\���݂̎��Ã��f���́u�헪�I���Ã��f���v�A�uMRI(Mental Research Institute)���f���v�A�u�����u�����f���v��w�i�Ƃ���
�@�@�@�\�헪�I���Ã��f���͖��̍���Ɉ��̍\�������肵�A�\���̕ω��ɓ��������悤�Ƃ������
�@�@�@�\MRI�͑��ݍ�p�̘A����l�̔F�m�̕ϗe���d��
�@�@�@�\�����u�����f���͎��Î҂ƃN���C�G���g���R�~���j�P�[�V������ʂ��āA�݂��̎�ς��\�����錻����V���Ȍ����ɍ��ς���
�@�@�\�ȉ��̂悤�ȕ��@�_������
�@�@�@�\��@����@�A�u���[�t�T�C�R�Z���s�[�A�ً}�u���[�t�T�C�R�Z���s�[�A�Z���S���Ö@�A�œ_���S�Ö@�A���Ԑ����S���Ö@
�@�@�\8����x�̖ʐڂ�7�����x�̖��̉��P��������Ƃ����
�@�@�u���[�t�T�C�R�Z���s�[�̋Z�@
�@�@�\���Î҂͉�b�����[�h���A�N���C�G���g�������������Ă�����悤�ɓ������߁A�ȉ��̂悤�ȋZ�@��p����
�@�@�@�\�u��O�������鎿��v�A�u�~���N���E�N�G�X�`�����v�Ȃǂ̎���Z�@
�@�@�@�\�������ɏœ_�����Ă�����Z�@(�R���v�������g�ƁA�\�z�̉ۑ�etc�c�c)
�Ƒ��Ö@�E�v�w�Ö@�E�V�X�e���Y�A�v���[�`
�@�\�v�w�E�Ƒ����V�X�e���Ƒ����đΉ����鎡�Ö@
�@�@�\�V�X�e���Ƃ́u�݂��ɊW�����������A�܂����Ƃ��W�������đ��݂����g�̗v�f�v�ƒ�`�����
�@�@�\�u��ʃV�X�e�����_�v��u��ʐ����̃V�X�e�����_�v�Ȃǂ������̖��ɉ��p����ꍇ���V�X�e���Y�A�v���[�`�ƌĂ�
�@ �V�X�e���Y�A�v���[�`�𗝉����邽�߂ɕK�v�ȊT�O
�@�@�J���V�X�e��
�@�@�@�\���Ƃ̊Ԃŕ����E�G�l���M�[�Ə�����ɂ��Ƃ肵�Ă���V�X�e���̂��Ƃł���A�����̃V�X�e���͑S�Ă���Ɋ܂܂��
�@�@�~�I���ʗ�
�@�@�@�\�V�X�e���̗v�f���݂��ɊW�����������Ă��邱�Ƃ����ʂ̊ϓ_����\�������T�O
�@�@�@�@e.g., �Ƒ��̈ꐬ���̍s�������̐����̍s���̌��ʂł���Ɠ����Ɍ����ɂ��Ȃ��Ă����Ƃ����W
�@�@�K�w��
�@�@�@�\�V�X�e���ɂ͂��P���Ń~�N���ȉ��ʃV�X�e������A��蕡�G�Ń}�N���ȏ�ʃV�X�e���܂Ŗ����̊K�w������
�@�@�@�\���郌�x���ɒ��ڂ����ꍇ�A���ʂ̃V�X�e���͂��̗v�f�ƂȂ�A��ʂ̃V�X�e���͂��̊���^����Ƃ����W�ɂȂ�
�@�@�@�@�\�l�ɑ������ɂ����āA�Ƒ���E��Ȃǂ̏�ʃV�X�e���A�Ȃǂ̌l�̉��ʃV�X�e���ɉ���\�ɂȂ�
�@�@�����̃V�X�e���Ǝ��Í\��
�@�@�\�����̃V�X�e���͈ȉ��̂R�\���������A�ǂ̑��ʂɒ��ڂ��邩�ʼnƑ��Ö@�̎�v�Ȋw�h�̈Ⴂ��������
�@�@�@�\��: ���鎞�_�ł̐Î~�I�ȃV�X�e���̗l��
�@�@�@�@�\: ������x�̋K�����������ČJ��Ԃ����o�����̃p�^�[��
�@�@�@���B: ���ԓI�o�߂ƂƂ��ɃV�X�e���̗v�f���S�̂��番�����܂��������Ă����ߒ�
�@�@�\�Ƒ��Ö@�̎��Éߒ��̗����ɑ傫���𗧂u�����ԁv�Ɓu�K���ߒ��v�̊T�O
�@�@�@������
�@�@�@�\�~�N���Ɍ���Ə�ɕϓ����Ȃ�����S�̓I�ɂ͂��ꂪ���͈̔͂Ɏ��܂�P�퐫���ێ������V�X�e���̐���
�@�@�@�K���ߒ�
�@�@�@�\�V�X�e�������O�̕ω��ɐ₦���Ή����Ĉ����Ԃ�ۂƂ��Ƃ���ߒ����Ӗ����Ă���
�@�@�@�@�\���̃t�B�[�h�o�b�N�ɂ��]���̈����Ԃ��ێ����悤�Ƃ��郂�[�t�H�X�^�V�X
�@�@�@�@�\���̃t�B�[�h�o�b�N�ɂ��V���Ȉ����Ԃ����o�����Ƃ��郂�[�t�H�W�F�l�V�X���܂܂��
�@�@�@�@e.g., �Ƒ������̐��_�a�Ȃǂ́A�Ⴆ�Ύq�ǂ��̎����ȂljƑ��V�X�e�����傫���ω����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��ɁA
�@�@�@�@�@�@�@�Ƒ����a�I�ɓK���ߒ������Ă��錻��Ɨ��������
�@�@�@�@���Ƒ��Ö@�̖ڎw���Ƃ���́A���㏞�̏��Ȃ��K�����Ƒ��ɂ����炷����
�@�@�Ƒ��Ö@�̓K�p
�@�@�\���������ǁA�ېH��Q�A�o�Z���ۂȂǂɓ��ɗL��
�@�@�\�����E�v�t���Ȃǂ̔N��̐S�g�ǁA�_�o�ǁA���a�A���s���Ȃǂɂ��L��
�@�@�\�v�w�Ö@�́A���ɃA���R�[���ˑ��A���a�A���@�\�ُ�ɗL���Ƃ���邪�A�v�w�Ԃ̕s�a�Ɋ�Â��l�X�Ȗ��ɗL��
�Ö��Ö@
�@�\�S���Ö@�̒��ł͍ł����j�̂�����̂ŁA���̌��_�Ƃ�������
�@�\J.A.�V�����R�[��A.A.���G�{�[��ɂ���āA�Ö��̌��ʂ͈Î��ɂ���Đ�������̂ł���Ƃ̍l�������L�܂���
�@�@�\S.�t���C�g�́A�ŏ��Ö��Ö@�̌��������Ă������A���̌㎩�R�A�z�@��҂ݏo���A���_���͂ւƂ��̍l�����W�����Ă�����
�@�\�Ö��Ö@�ɂ���āAJ.H.�V�����c�ɂ�鎩���P���@�̊J���AE.R.�q���K�[�h�̎����I�����AM.H.�G���N�\���̍Ö��Ö@�����W����
�@�@�Ö��Ƃ͉���
�@�@�\����̑����A�v���[�`�����A������Ƃ����Ȋw�I�ȗ��t���̂������
�@�@�\�Ö��́u����Î��ɂ���Đl�דI�ɂЂ��N���ꂽ�ӎ��̕ϗe��ԁv�ł���ƒ�`�����
�@�@�@�\�����Ɨގ����Ă��邪�A�َ��̂���
�@�@�@�\�Ö����͔�Î��������ɍ����A�o�����ɔ�ׂĉ^���A�m�o�A�v�l�ُ̈퐫���e�ՂɈ����N�������
�@�@�@�\�ӎ��̕ϗe��Ԃ��Ö����g�����X��ԂƂ���
�@�@�\�Ö���Ԃ̓����Ƃ��āA�C���[�W�̊������A�S�g�̃����b�N�X��ԁA���ӏW�����I�ł������Ȃ邱�ƂȂ�
�@�@�\�Ö���Ԃւ̗U���ɂ́A�ʏ�Ö��U���̂��߂Ɍ��܂�����A�̈Î��n����A����ɏ]�����ƂōÖ��[�x���[�܂�
�@�@�Ö��Ö@�̋Z�@
�@�@�\�Ö��Ö@�ɂ͑�ʂ����2�̕��@������
�@�@�@1. �Ö����̂��̂������ÓI�v�����ő���ɗ��p���悤�Ƃ������
�@�@�@�@e.g., �Î��ɂ���ďǏ���������悤�Ƃ�����́A�C���[�W�𗘗p�������(�����^���E���n�[�T��)�A�����Ö��Ö@etc�c
�@�@�@2. ���̗Ö@�̒��ɍÖ���g�ݍ��݁A���̗����̌��ʂ����߂悤�Ƃ������
�X�c�Ö@
�@�\�X�c���n�ɂ���đn�n���ꂽ���_�Ö@
�@�\�_�o�ǁA�Ƃ��ɎЉ�|�X������������ɑ������Ö@
�@�\�X�c�̌��@�́A�ȉ���4���ɕ������
�@�@1. ����: ��Ή����
�@�@�\�N���C�G���g���u�����A���������ȊO�ɂ͈�̊����𐧌����A�قƂ�Ǖz�c�ɐQ�Ă���悤�ɑ���
�@�@2. ����: �y��Ɗ�
�@�@�\���Ԃ�7�`8���Ԃɂ��A�O�E�̎����߂���y��Ƃ��������肷��
�@�@3. ��O��: �d��Ɗ�
�@�@�\�������ԈȊO�͐₦���������s���Ă��鐶���������A����ɓ��̓I�Ȏv����ƂɎʂ��Ă����B�Ǐ��A��Ȃǂ����R�ɂ�����
�@�@4. ��l��: �މ@������
�@�@�\���퐶���ɕ��A�����A�����P�����s���B
�@�@�@�\��ꂩ���O����P�R�[�X�Ƃ��Ď��Â���������悤�ɂ���
�@�@�@�\���̊ԁA�������������A���Îґ��̌o�ߊώ@�ɂ���ƂƂ��ɁA���҂̎��ȓ��@��[�߂�悤�ȃR�����g��^����
�@�@�X�c�_�o��
�@�@�\�X�c�Ö@�͐X�c�_�o���ƌĂԐ_�o�ǂ̒��̈�Q��ΏۂƂ��Ă���
�@�@�@�\�X�c�_�o���́A�f���ɋ@��^�����A���_���ݍ�p�ɂ���Ĉ������Ă�������
�@�@�@�@�\�u�f���v�́A�����̏�������ɔے�I�ł���ƌ��߂���X���ł���A�u�q�|�R���f���[�C���v�ƌĂ�
�@�@�@�@�\�u���_���ݍ�p�v�Ƃ́A�����̏�I�����Ɉӎ����W��������قǁA��I�����������������鈫�z���N���邱��
�@�@�u���邪�܂܁v�Ɓu���ւ̗~�]�v
�@�@�\�X�c�Ö@�ł́A���_���ݍ�p��ł���A���̐l���{�������Ă��錒�N�I�ȗ́A�u���ւ̗~�]�v�������o�����Ƃ𒆐S�ۑ�ɂ���
�@�@�@�\�s�����u���邪�܂܁v�Ɏ���āA���ǂ��Ȃ肽���Ƃ����u���̗~�]�v�ɏ]���čs�����邱�Ƃ�̓�������
���ϗÖ@
�@�\���Ƃ��Ƃ͋g�{�ɐM�ɂ��A��y�^�@�́u�����ׁv�����Ƃɂ��ĊJ�����ꂽ�C�{�@
�@�\���_�Ö@�Ƃ��Ă̌��p���F�߂��A���݂ł͍��ۓI�ɂ��]���Ă���
�@�@���ϗÖ@�̎葱
�@�@�\�����̐g�߂ȕ�A���A�v�܂��͍ȁA�q�A�搶�Ȃǂɑ���ߋ��̊ւ����ȉ���3�̃e�[�}�ɉ����ČJ��Ԃ��v���o�����@
�@�@�@1. ���b�ɂȂ�������
�@�@�@2. ���ĕԂ�������
�@�@�@3. ���f������������
�@�@�@�\��������͂̐l�X�ւ̗������[�܂�A�����ȋC�����ɂȂ�A�l�Ԃւ̐M�������A���Ȃ̐ӔC�����o���A�ӗ~�I�ȍs�����ł���
�@�@�\��̓I�ȕ��@�́u�W�����ρv�Ɓu������ρv�ɕ������
�@�@�@�\�W������
�@�@�@�@�\���ϓ���ɂP�T�ԂƂǂ܂��Ď��{����
�@�@�@�@�\�O������̎h�����Ւf�������Â������Â��ț����Ɉ͂܂ꂽ��Ԃōs��
�@�@�@�@�\�������U�������X���܂Ōp���I�ɁA�R�̃e�[�}�Ɋւ���̓I�������A�ߋ����猻�݂܂łR�`�T�N���݂Ŏv���o��
�@�@�@�@�\������P�`�Q���Ԃ��ƂɖK���ʐڎ҂Ɏ�Z�ɕ��A�ʐڎ҂͕��e�ɋ����I�Ɏ����X���A���̃e�[�}���m�F�A���シ��
�@�@���ϗÖ@�̓K�p
�@�@�\��ʐl�̐l�i�̓����A�C�{�A�l����̔Y�݂̉���
�@�@�\�s�o�Z���s�A�ېH��Q�A�e�q��v�w�̕s�a�A����ԁA�A���R�[����ˑ��A�S�g�ǁA�_�o�ǂȂǂɗL��
��H�Ö@(Fasting Therapy)
�@�\��H�ɂ��A�����_�o�@�\�A������@�\�A�Ɖu�@�\�Ȃǂ̐g�̋@�\�̍Ē����������鎡�Ö@
�@�\�S���Ö@�Ƃ��Ă̈Ӗ�����������
�@�@�\���҂̋C�Â�����Ȃ𑝂��A�F�m�I�đ̐��������i����A�\�����Ǝ��M�̊l���A���ȊT�O�̗ǍD���A�����K���͑��傪�}����
�@�@�\�����P���@�A���ϖ@�A�Ǐ��Ö@�Ȃǂ̐S���Ö@�ƕ��p�����ꍇ������
�@�@��H�Ö@�̎葱
�@�@1. ���҂��K���ǂł���Ɣ��f���ꂽ�ꍇ�ɂ́A���Âɑ��铮�@�Â���}��A�S�g���ʂł̐������s����
�@�@2. ���̌�A10���Ԃ̐�H����5���Ԃ̕��H���A�����ĉ����ݒ肳���
�@�@�@2-1. ��H��
�@�@�@�\��H���ɂ͊��҂����Ɋu�����A�ʉ�A�d�b�A�e���r�Ȃǂ̎Љ�I�h���͋֎~�����
�@�@�@�\����𒆎~���A5�Y����t500�`1000ml�Ɋe��r�^�~���E�A�~�m�_��Y�������_�H���s��
�@�@�@�@�\���̎��A�������ȊO�̈��H���̐ێ�͋֎~
�@�@�@2-2. ���H��
�@�@�@�\������A������A�����Ȃǂ̕��H���j���[�ɏ]�����H���������
�@�@�@2-3. ��
�@�@�@�\�Љ�A�ւ̌P���A�Ö@�̍ĊJ�A�S�g���ʂ̐������s����
�@�@��H�Ö@�̓K�p
�@�@�\�ߕq�����nj�Q��ߊ��C�nj�Q�Ȃǂ̋@�\�������ւ̓K�p
�@�@�\�����_�o�����ǁA�؋ْ������ɁA�A�����M�[�����A�ꕔ�̐ېH��Q�Ȃǂ̓K���Ǔ��ւ̓K�p�����ʓI
�@�@�\�M�������A�o���̋��������A��������ᇁA�d�Ǎ������ǁA�S�؍[�ǂȂǂ̊펿�������A���������ǁA�����x�̂��a�Ȃǂ͋֊�
�Q�V���^���g�Ö@
�@�\�N���C�G���g�́u���A�����Łv�̑̌��ɂ��A���Ȃ̑S�̐��̉��d�����鎡�Ö@
�@�@�\�ߋ��̑̌����\���ɏ������ꂸ�u�������Ȗ��v�ƂȂ��Ă��邽�߂ɁA�����̑S�̂Ŏ��R�ȑ̌����ł��Ȃ��Ȃ��Ă���ꍇ�ɗp����
�@�@�\�������Ȗ�肪�u���A�����Ɂv�\���ɗN���N���Ă���悤�ɂ��A���������邱�Ƃ�ڎw��
�@�@�@�˂������́u�}�v���Œ肵�Ă��܂��Ă����Ԃ��u�n�v�ɖ߂��āA�Ăю��R�Ȑ}�������Ԃɂ��邱�ƂƊT�O������Ă���
�@�Q�V���^���g�Ö@�̎葱
�@�\�O��
�@�@1. �Z���s�X�g�͕��́E���߂͂��Ȃ�
�@�@2. �N���C�G���g�������ւ̋C�Â���[�߂���悤�ɁA���S�ŐM���ł������
�@�\�N���C�G���g�́A����܂ňӎ�����r�����Ă��������Ɂu���A�����Łv�C�Â����Ƃ��o����ƁA�S�̂Ƃ��Ă̎�������������
�@�\�Z���s�X�g�̖���
�@�@1. �N���C�G���g�̕\�Ɍ��ꂽ���t��s�������łȂ��A���ْ��̌���Ȃǂɂ����ӂ������A�t�B�[�h�o�b�N
�@�@2. ���̈Ӗ���q�˂邱�ƂŁA�����̉ߒ�������
�@�\�`�F�A�E�e�N�j�b�N�Ȃǂ��p������
�@�Q�V���^���g�Ö@�̓K�p
�@�\�S�g�ǁA�_�o�ǁA���a�ȂǗl�X�ȐS���I���ɓK�p�����
�|�p�Ö@
�@�\��I�Ȏ��ȕ\���ɂ���Ė���Ǐ�̔w��ɂ���S���I�����U������
�@�@�\���t�ɂ���Č������@�艺���Ă����ߒ��ɂ���Ď��ȓ��@�𑣂��A�����̃J�E���Z�����O�ߒ��Ƃ͈قȂ�
�@�\�l�Ԃ����������Ă���A���ʂɍ݂���̂����炩�̌`�ŕ\���������Ƃ����~������b�ɂ����S���Ö@
�@�@�\�������������A�G�ŕ\�����邱�Ƃɂ���āA���ʂɒ~�ς��ꂽ�]��ȃG�l���M�[�̉��(����)�A�S�I�ْ��������ق���(�J�^���V�X)
�@���ꉻ���ɂ������ʂ̖��ɋC�Â����߂̎藧��
�@�\���ËZ�@�Ƃ��Ă����ł͂Ȃ��A�L���Ȑf�f�@�Ƃ��Ă̑��ʂ�����
�@�@�\����ɂ��ΐl�I�ڐG�����ȑ�l�ɑ��āA�܂�����\���̓���c���⎙���ɑ��Ė{���I�Ȗ��m�����Ă���
�@�@�\�ʏ�͈ӎ����ɗ}������Ă���S�I�������\�o����邱�Ƃ�
�@�@�@�ˌ|�p��ʂ����R�~���j�P�[�V�������A����I�Ȑf�f��Ö@�ȏ�ɗL�v�ȕ��@�ƂȂ邱�Ƃ�����
�@���܂��܂Ȍ|�p�Ö@
�@�\���̎��
�@�@�\�G��Ö@�A����Ö@�A���y�Ö@�A���`�Ö@�A�R���[�W���Ö@etc�c�c
�@�\���{�̌`��
�@�@�\�l�\�W�c�A���炩�̉ۑ�ɉ����ꍇ�\�N���C�G���g�̎��R�Ȕ������d������ꍇ
�@�|�p�Ö@�̖ړI
�@�\�ǂ̂悤�ȖړI�ɂ���Č|�p�Ö@��p���邩�́A���Ö@�̕��@�_�ɂ���ĈقȂ�
�@�\�ȉ��̂悤�ɋ��ʂ���v�f������
�@�@1. �N���C�G���g�Ǝ��Î҂̊���𗬂𑣐i����
�@�@2. �N���C�G���g�̓��ʂɑ��݂��邪����I�\��������Ȗ��_�m�ɂ���
�@�@3. �N���C�G���g�̊S������̓��ʂɌ����A���@�𑣂�
�@�@4. ���ӎ��܂��͕a������������
�@�|�p�Ö@�̓K�p
�@�\�_�o�ǁA�S�������A�S�g�ǁA���a�A�������ɂ����铝�������ǂƂ��������_��w�I�Ǐ��A�����E���k�̕s�K���s���ɗL��
�@�\�f�f�I�ȗ��p�̏ꍇ�́A���炩�̉ۑ����I�v�f���܂ޕ����K���Ă���
�@�\���ËZ�@�Ƃ��ėp����ꍇ�́A���R�Ȕ����������o���₷���Z�@���I�������
�@�\����@�\�̐Ǝ�ȃN���C�G���g�́A����Ȗh�q������Ɏ�̉����A�댯�ȏ�Ԃ��������Ƃ����邽�ߒ��ӂ��K�v
�V�Y�Ö@
�@�\�V�т�}��Ƃ��čs����S���Ö@
�@�@�\�q�ǂ���ΏۂƂ��Ď��{����邱�Ƃ�����
�@�\���ÊW�ɂ����ẮA�s����ْ��̉����ɉ����A���Î҂̉����̂��ƂŎ����̊���߂⌻���ւ̑Ώ��̎d�����w��
�@�V�Y�Ö@�̗��j�ƋZ�@
�@�\H.�t�b�N - �w�����[�g(1913)�ɂ���Ďn�߂��AA.�t���C�g��V.M.�A�N�X���C���ɂ���Ĕ��W���ꂽ
�@�\�V�Y�Ö@�̗���ɂ́A���_���͗Ö@�A����Ö@�A�W�Ö@�A�������S�I�Ö@�A�ܒ��I�Ö@������A����ɂ���ċZ�p�͈قȂ�
�@�@�\�Z�p�̑���́A�����������邩�̈Ⴂ
�@�@1. �V�т��̂��̂̎��̌����p�̋���: �q�ǂ��̎������ɔC����
�@�@2. ����̔��U���ʂ̋���: �V�тɂ���ĕs����s���̉�����}��
�@�@3. ���Â̊W���̋���: ���Î҂Ƃ̗ǍD�ȊW��̌�����
�@�@4. ����I���ʂ�w�K�̋���: �q�ǂ��Ɍ����ւ̑Ώ����@��������
�@�\���낢��ȗV���^�����R�ɗV���鎩�R�V�Y�Ö@�ƁA�Ƒ��l�`��S�y�ȂǓ���̗V��Ɍ���V���鐧���I�V�Y�Ö@������
�@�\�l�Ö@�Ƃ��Ă��W�c�Ö@�Ƃ��Ă��s����
�@�\�q�ǂ��̎��Âł́A�ی�҂̃J�E���Z�����O�����s���Đi�߂���ꍇ������
�Ǐ��Ö@
�@�\�J�E���Z�����O�̉ߒ��ŃN���C�G���g�ɓ���̕����ǂ܂��A�����ʂ��āA�ڕW�ɓ��B���邽�߂ɕK�v�ȓ��@����
�@�@�\�����̓o��l���̓��ʂ�T�ώ҂̗���œǂނ��Ƃ��ł��A�������┽���Ȃ��ɑ��҂̓��I���ʂ𗦒��Ɏ������
�@�Ǐ��Ö@�ɉ������҂��邩
�@1. �o��l���Ǝ��Ȃꎋ���A�ᔻ�I�Ɍ��Ƃ��́A�N���C�G���g���g������̖��@���A�ēK���ւ̓��@�Â�������
�@2. ����̒�����A�N���C�G���g���g�̖������ɕK�v�ȏ���
�@3. �쒆�Ŏ������l�X�ȏ�ʂɂ�����A�o��l���̐U�镑���⊴��\����ʂ��ēK���I�ȉ��l�̔��f���
�@4. �}������Ă���~���̏[�����A�����̓o��l���ɓ��e���邱�ƂŊԐړI�ɍs��
�@�Ǐ��Ö@�̎葱
�@�\�N���C�G���g�̖��ɉ����ēK����I�肵�A�K�v�ɉ����Ăǂ̂悤�ȑԓx�œǂݐi�ނׂ���������
�@�@�\�nj�͂��̍�i�ɂ��Ęb����������A�ꍇ�ɂ���Ă͊��z������������(�u�U��Ԃ�v�̉ߒ�)
�@�@�˃N���C�G���g�͎��ȓ��@�ɂ�����肪���������̎�Ŋm�F���Ă���
�@�\�ǂݕ��̑I���ɂ�����A�N���C�G���g�̖��ɒ��ڊW�̂��鎖��������Ƃ���������I�����邩�͏ɂ���ĈقȂ�
�@�@e.g., �J�E���Z�����O�̐i���A�N���C�G���g�̃p�[�\�i���e�B�v��etc�c�c
���p����:  �A�Տ��S���w�L�[���[�h (�L��t�o���\KEYWORD SERIES)
�A�Տ��S���w�L�[���[�h (�L��t�o���\KEYWORD SERIES)
Keyword: �𗬕��́A�W�c���_�Ö@�A�T�C�R�h���}�A�X�g���X�Ɖu�P���A�������Ö@�A�ΐl�W�Ö@�A�����P���@�A�o�C�I�E�t�B�[�h�o�b�N�A�u���[�t�T�C�R�Z���s�[�A�Ƒ��Ö@�A�V�X�e���Y�A�v���[�`�A�Ö��Ö@�A�X�c�Ö@�A���ϗÖ@�A��H�Ö@�A�Q�V���^���g�Ö@�A�|�p�Ö@�A�V�Y�Ö@�A�Ǐ��Ö@
���Տ��S���w�̗p��ꗗ��